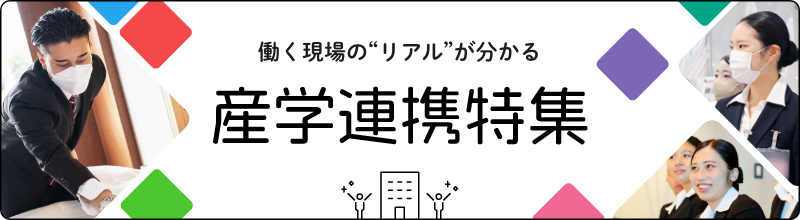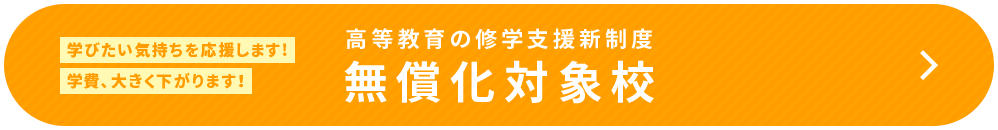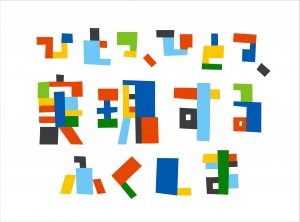
つなぐ福島
「福島の今」を知った私たちが未来へつなぐ「震災の教訓」と「福島の魅力」
協力企業・団体
福島県 / 福島市観光コンベンション協会 / ラジオ福島 / ふくしま果樹加工考案室 /観光農園スマイルファーム / BOND&CO. /大阪市北区役所 / 大阪市北区社会福祉協議会 / 一般社団法人ドローン減災士協会 / 大阪北区ジシン本 / 一般社団法人 あおぞら湯 / J:COM株式会社 / オーエス株式会社 / 関西福島県人会 (順不同・一部抜粋)
2024年9月、学校法人山口学園と福島県は「関西地方で福島の情報発信を継続的に実施すること」を目的とした協定を締結。福島の風評風化対策や、現状を研究する授業「つなぐ福島」を開講しました※。受講生9名は実際に福島を訪れ、被災当時の様子や風評被害など、震災から復興への歩み、そして福島の今について学びました。農家の方々から、安心安全のため様々な困難と努力について直接お聞きし、その胸の内を知る貴重な時間を過ごしました。震災直後からたびたび報道され、聞き覚えのある「双葉町」や「浪江町」にも足を運び、原子力災害伝承館などを視察し「震災が起きた事実」をしっかりと肌で感じました。観光地としての福島県の「魅力」と「復興のあゆみ」について、より多くの人々に知ってもらうため、自分たちの目に映った景色や食のおいしさ、胸を打たれた思いを、受講生みんなで発信しました。※2024年度より選択授業として開講、全コースの学生が参加できます。

大阪から新幹線を乗り継いで約4時間。たどり着いた自然豊かな福島県にある「まるせい果樹園」さんにて桃や梨の収穫を体験させていただきました。果実の甘さに「世界で一番おいしい!」と声を上げる学生たち。原発事故の風評被害による経営困難を乗り越え、より安心安全のために尽力する農家さんのお話に、学生たちは心を動かされた様子でした。
東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)では、震災当時の写真や映像の展示を見学。今、目の前に広がる美しい草原は、14年前の震災が変えてしまった景色でもあります。もし、震災がなければどんな光景があったのか?実際にその場に立つことで感じる「震災」に、涙をこぼす学生の姿もありました。
福島県・内堀雅雄知事のもとへ表敬訪問。学生たちは原子力災害伝承館など現地での感想を直接知事へと伝えました。知事の「福島の人は福島プライドを持ち、困難に立ち向かってきた」というお言葉から、今も復興に向け歩み続ける県民の方々の思いを強く感じました。
「福島は空気がおいしい」という学生の言葉に、知事は「実際に来ないとわからない感想。来てもらうためのキラーワードになる。ぜひ広報に使いたい!」と喜んでくださいました。「農作物は届けられても、空気は缶に詰められないから…」とのお言葉には会場が和みました。
11月。大阪・梅田にて福島銘産市「ふくしまマルシェ」を開催!お米、日本酒、フルーツをふんだんに使ったドリンクなどなど福島が誇る名産品の数々を販売しました。福島からお越しくださった県民の方々や、関西在住の福島県民の方々にご協力いただききながら、福島の魅力を発信しました。また、マルシェを開催した梅田は大阪市北区にあり、多くの人々が集います。「大阪北区ジシン本」のブースを設置し、地震や災害を身近に感じてもらう場も設けました。
マルシェでは、ラジオ福島のご協力のもと「Radio de Show」の公開収録を行いました!福島出身のタレント・なすびさま(写真:左)には本校へもお越し頂き、故郷・福島、そして復興についてお話し頂きました。「お金を送ることだけが復興支援ではない」との言葉は、学生たちが支援について改めて考えるきっかけとなりました。
1月には北区民センターで開催された「ふくし防災フェスタ」に参加しました。震災時によく使われる「避難」「炊き出し」などの日本語。実は海外の人にとって聞きなれないため、理解が難しい言葉もあるそうです。こういった状況を知ってもらおうと、留学生にもイベントに参加してもらい、避難所でよく使う日本語を6ヶ国語に訳し、展示しました。
避難時にどう説明すればよいか考えるきっかけになれば、と学生たちは「やさしい日本語へ言い換えクイズ」を考案。「直ちに避難」は「早く逃げる」など、わかりやすい言葉へ言い換えるクイズです。海外の方々だけでなく、子どもにも伝わりやすそうですね。では「救援物資」。皆さんはどう「やさしい日本語」にしますか?
2月。「つなぐ福島」活動成果発表を行いました。会場には、ご協力いただいた企業・団体の皆さまにもお越しいただきました。「福島産の食品は食べられない」と言う韓国人の友人へ、自分にも返す言葉がないと気が付き、受講したと話す学生。震災を風化させてはいけない思いを込めながら「福島は自然が美しく美味しいものもたくさん。ぜひ訪れてほしい」と発表を締めくくりました。
今回の研修で「災害を自分事ととらえることが大切」と感じた学生たち。ITを使った支援や、子どもの心のケアを目指すなど、それぞれの方法で福島の復興につなげていこうと思いを新たにしたようです。福島県の方から「福島を思い続けることが、福島の力になる」というメッセージをいただき、学生たちも力強く頷いていました。学生たちの今後の活躍、そして福島の復興を願います。